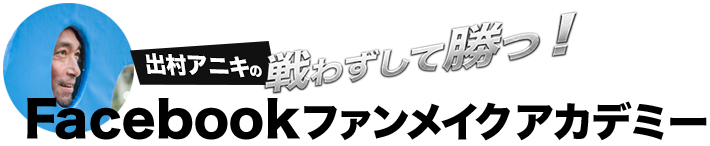デジタル格差とは、誰に聞いたらいいの?

誰に聞けばいいの?デジタル格差を考える
インターネット社会の拡がりにより生まれてきた情報格差
総務省の情報通信白書では「デジタル・ディバイド(情報格差)」
例えば、
このような課題は年代だけではありません。個人レベル、家庭間、
国際的なデジタル格差
ビジネスの場がオンラインに移ったおかげで、
端的に言うならば、日本に住む人たちは、
つい7月にアメリカ留学から帰国した女性が言っていました。「
言い換えれば日本人はまだまだ伸び代があるのかもしれません。
家庭間のデジタル格差
PTAに携わっていて痛感したの家庭…、とりわけここでは“親”
知らないことは知らないと、
この親の問題は、子どもに影響してしまいます。
一方で、家庭にインターネットやデバイスが普及している割合は、
教育現場でのデジタル格差
日本の教育のICT化に、
とはいえ教育現場にもネット社会の普及に対する「デジタル・
公立の小中学校は一人一台のタブレットが支給されるようになりま
必然的に教える方にも、
教える側も教えられる側も、今やスマホやタブレット、
貧困の差によるデジタル格差
インターネットからあらゆる情報が得られるからこそ起こる情報の
単なるニュースや天気予報だけではありません。
他人では踏み入れないセンシティブでプライベートな課題であるが
置いてけぼりな高齢者問題
若者や30代40代とくらべて、
これから社会のサービスはますますスマホを通して行われることに
先日 こんな話を伺いました。
未来の子供達を救う
2010年以降に生まれた今の小学生は、「AIネイティブ」
我が家の愛娘にはまだスマホを持たせておりませんが、
言わずもがな、
時代を先導する役割
今私たちは、大きな時代の潮流にいます
・新型ウイルス
・気象変動
・テクノロジーの進化
「そんなの絶対に太刀打ち出来ない!」なんて思うなかれ
ひとりのチカラでは限界があるかもしれない。
時代に流れについて行けないと感じるかもしれない。
また変わるのか…と不安に思うかもしれない。しかし“知れ”
人類はこれまでも幾多の困難を乗り越えてきたのです。
次の世代に何を手渡すか、今日も考えて、一歩を踏み出す
“一家に一法人” どころか “一人一法人の時代”
詳しくは毎月人気のオンラインセミナーで!
↓↓
集客と節税をコントロールして資金調達する
Tax Saving Practices
『TSPオンラインセミナー』